H29年11月21日、奥久慈男体山付近を散策してきた。
奥久慈の紅葉は見頃に入っている。
奥久慈は広く多くの紅葉スポットが点在していて、場所を選べば長く紅葉を楽しめる。
今回は奥久慈男体山付近のスポットを散策した。
大円地登山口7:50~一般コース~大円地越8:45~表縦走路~小草越9:40~裏縦走路~10:40支尾根(昼食)11:15~沢~曽根越11:45~12:00鷹取岩12:10~フジイ越12:25~古分屋敷12:50~12:55大円地登山口
約5時間の紅葉散歩でした。
山行記録 地域別山行記録 奥久慈男体山記録
![]()
冷え込みがきつい大円地をスタート。久しぶりに一般コースを行く
![]()
大円地越直下のモミジ谷。
ピーク時にはモミジの大木が真っ赤に染まる場所であるが、まだ青々としている。
![]()
![]()
![]()
大円地越。男体山へは向かわず縦走路を南下する。
![]()
表縦走路に入り直ぐに、一角に綺麗な紅葉が広がっていた。
![]()
表縦走路のモミジ谷に着く。色付きは今一つ、青みも多くピークはこれからですね。
![]()
![]()
![]()
小草越から紅葉の森を纏った男体山が綺麗です。
![]()
裏縦走路のモミジ谷の上部に着く。尾根の左側の斜面は綺麗ですが
![]()
尾根の右側のモミジ谷は真っ青。これはダメだ~と渡り歩いて支尾根へ
![]()
この支尾根は歩く人もいない、ザックを降ろして紅葉真っ盛りの尾根をウロウロ
![]()
![]()
![]()
![]()
この紅葉に囲まれて昼食。食後のコーヒーは格別だ。
![]()
食後に寝転んで見上げると真っ赤
![]()
下山はこの尾根を降る。ヤブっぽい尾根だが紅葉が良い感じ
![]()
![]()
![]()
尾根の紅葉が良さそうな所を選びながら
![]()
![]()
沢に降りたつ。水量が少なく容易に渡れる。
![]()
沢から荒れた斜面を登り曽根越に飛び出る。曽根越付近の紅葉が綺麗です。
![]()
![]()
縦走路を北上し鷹取岩へ。鷹取岩の崩落は進んでいてピークに立つのは怖いくらいだ
![]()
フジイ越から古分屋敷へ
![]()
古分屋敷への登山道の紅葉もまずまず
![]()
![]()
朝方は冷たかったが日中は穏やかな天気に恵まれ紅葉日和でした。
まずまずの紅葉に満足でした。また他のルートを歩いてみよう。
奥久慈の紅葉は見頃に入っている。
奥久慈は広く多くの紅葉スポットが点在していて、場所を選べば長く紅葉を楽しめる。
今回は奥久慈男体山付近のスポットを散策した。
大円地登山口7:50~一般コース~大円地越8:45~表縦走路~小草越9:40~裏縦走路~10:40支尾根(昼食)11:15~沢~曽根越11:45~12:00鷹取岩12:10~フジイ越12:25~古分屋敷12:50~12:55大円地登山口
約5時間の紅葉散歩でした。
山行記録 地域別山行記録 奥久慈男体山記録

冷え込みがきつい大円地をスタート。久しぶりに一般コースを行く

大円地越直下のモミジ谷。
ピーク時にはモミジの大木が真っ赤に染まる場所であるが、まだ青々としている。



大円地越。男体山へは向かわず縦走路を南下する。

表縦走路に入り直ぐに、一角に綺麗な紅葉が広がっていた。

表縦走路のモミジ谷に着く。色付きは今一つ、青みも多くピークはこれからですね。



小草越から紅葉の森を纏った男体山が綺麗です。

裏縦走路のモミジ谷の上部に着く。尾根の左側の斜面は綺麗ですが

尾根の右側のモミジ谷は真っ青。これはダメだ~と渡り歩いて支尾根へ
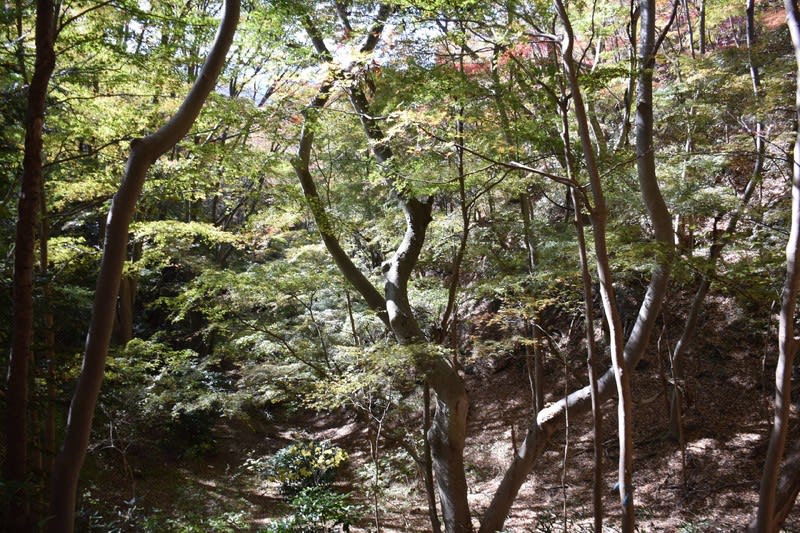
この支尾根は歩く人もいない、ザックを降ろして紅葉真っ盛りの尾根をウロウロ




この紅葉に囲まれて昼食。食後のコーヒーは格別だ。

食後に寝転んで見上げると真っ赤

下山はこの尾根を降る。ヤブっぽい尾根だが紅葉が良い感じ



尾根の紅葉が良さそうな所を選びながら


沢に降りたつ。水量が少なく容易に渡れる。

沢から荒れた斜面を登り曽根越に飛び出る。曽根越付近の紅葉が綺麗です。


縦走路を北上し鷹取岩へ。鷹取岩の崩落は進んでいてピークに立つのは怖いくらいだ

フジイ越から古分屋敷へ

古分屋敷への登山道の紅葉もまずまず


朝方は冷たかったが日中は穏やかな天気に恵まれ紅葉日和でした。
まずまずの紅葉に満足でした。また他のルートを歩いてみよう。














































































































































































































































































































































































































































































































